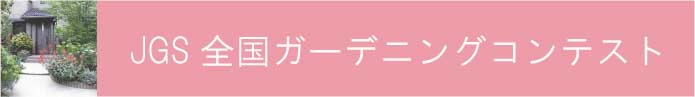◇ 6月のバラの手入れポイント ◇
華やかに咲き誇っていたバラはほとんどのものは5月中旬から下旬に終わり、6月には遅咲きのグループが開花を続けてくれます。ブラインドを処理した枝はこの月に小ぶりながらしっかりした花を咲かせます。葉が十分茂っている株からはシュートの発生が盛んになり、この時期は咲きがら摘みとシュート・ピンチや除草などの作業がたくさんあり、中旬には梅雨に入るので、その前に済ませておきたいものです。ウドンコ病のほか黒点病の発生も目立ってきますので、入梅後の定期散布も予定をしっかり立てて実施します。
■咲きがら摘み
先月に引き続き咲きがらをこまめに摘んでやります。咲き終わった花枝は5枚葉を1枚つけてカットします。まだ苗の段階の株や切花を採りすぎた株は葉をなるべく残したいので最初の5枚葉の上で切ります。つるバラやシュラブも四季咲き性のものはヒップ(実)をつけると新しい枝の伸長が止まって咲かなくなるので、ほとんどの花が終わったら1回、徹底的に行います。一季咲きのものや野生種はこれを行わず、実を付けさせたら秋に楽しめる上、夏の繁茂しすぎを抑制することができます。
■シュートの処理
一番花が終わるころから7月までがシュートの発生時期です。シュートは来年以降の幹となるので大切に育てます。HTやFLなどのブッシュではシュートをそのまま放置して箒状に花を咲かせると充実した幹になりにくいので、シュートが20㎝ほど伸びて先端に蕾が見えた頃まだ柔らかいうちに、先端を3-5㎝指で摘み、分枝させます。分枝で出た枝には花を咲かせてかまいません。これをシュートピンチといい、これをしないと箒状に沢山花を咲かせて幹は充実しません。ピンチは1回だけで十分です。ミニやシュラブやつるバラではこれを行わず、真っ直ぐ伸ばしてやります。また、この時期に蕾を持たないブラインドには5枚葉を1枚つけて切り戻しておくと6月中旬にはきりっとした花が咲きます。
■病虫害の防除
梅雨の時期は薬剤散布が予定通り行えないことが多いのですが、雨の合間を見てあまり間隔があかないよう努めます。この時期は黒点病、ウドンコ病が発生しますのでダコニールにそれぞれの治療剤を上乗せします。治療剤は散布後の効果を確認するため1週間観察します。効果が認められないなら別のグループの薬剤に切り替えます(ローテーション)。害虫では気温の上昇に伴ってハダニが急激に繁殖します。チュウレンジバチなどのほかに中旬以降ゴマダラカミキリが飛来して産卵します。この対策として殺虫剤をアドマイヤー、モスピラン、ダントツなどネオニコチノイドといわれる殺虫剤を間隔をあけて2回ほど散布して成虫を防除します。
■施肥と潅水
庭植えの株には冬の元肥を十分施してあれば、この時期には特に必要ありませんが、お礼肥をやるのであれば、1株あたり化成肥料(8-8-8)なら50gで十分でしょう。梅雨のさなかに夏の元肥と勧めている本もありますが、この時期は気温が高いので分解が進み、栄養の大部分が夏の栄養生長へ回ってしまいます。鉢植えには置き肥と液肥を復活させ、水遣りは梅雨時期なので過湿にならぬように与えます。鉢植えは、雨が降っても葉面積が増えているので、鉢に水が落ちない上に照ったら乾きやすくなっています。しおれすぎないように注意します。
■除草・清掃
気温の上昇に伴って雑草の生育は旺盛になるので早めの除草を心がけます。大きくならないうちに取るのが除草の基本です。また株元をいつもきれいに保つよう心がけましょう。
◎以上の作業は関東以西の作業となります。北の地方や降雪地帯にお住まいの方はテキスト2、112ページの平均気温表をご覧いただき、時期をずらして作業しましょう。