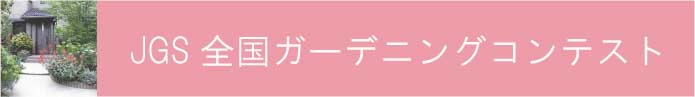◇ 5月のバラの手入れポイント ◇
待ちに待った5月、バラの季節の到来です。バラの生育に応じて手入れの方も忙しくなり、遅れないよう心がけます。ご自分の庭もさることながら、いろいろなバラ園や各地で開催される展覧会などへも出かけて見聞を深め、観賞眼を養いたいものです。
■開花の早晩
野生種は別にして、ゴールデンウイークに入ると早咲きのバラが咲いてきます。ポピュラーな品種ではマダムA・カリエール、ゴールデン・シャワーズ、いずれもつるバラです。また、1株の中で早く咲いたものをよく観察するとステムが短く、通常6~7枚はある葉が3~4枚で花芽がついているのが分かります。いわば発育不良、未熟児で花は小さく、花びらも少なめです。本来はこのような未熟枝が発生しないよう冬に剪定をするわけで、全体に早く咲くのは剪定が浅いということで自慢にはなりません。
■病害虫の防除
開花中は薬剤散布を控える人が多いのですが、この時期はバラにも病害虫にも快適な気候ですので定期散布を続け、開花中であっても1回は散布します。およそ3週間の開花期に1~2回の定期散布をやるか、やらないかで病害虫の発生がかなり違ってきます。花に薬液がかかっても殆ど汚れません。ウドンコ病対策としてはレシピにフルピカ、トリフミンなどの治療薬を上乗せします。また、黒点病の発生が見られたら広がらないうちにサプロールなどのEBI剤をレシピに加えます。気温が上がってくるので、下旬には一度ハダニ対策として殺ダニ剤を加えると被害を最小限に抑えられます。
■ブラインドの処理
花芽の付かなかった枝(ブラインド)は先端を5枚葉1枚付けてカットして切り戻しておきます。また、この時期にブラインドの側芽の発生を促すと6月中旬にはある程度立派な花が開花します。これを行わないと先端から2芽同時に伸びて貧弱な花を2輪咲かせます。対象は大輪種(HT)のみとなります。なお、春は樹勢が強いので台芽(台木の芽)が発生します。早めに掻き取らないとノバラに負けてしまいます。
■摘蕾
摘蕾は形がよく1輪が似合うHTだけに行い、一重のディンティ・ベスやクイーン・エリザベスなどは対象になりません。ゴールデンウイークがこの作業のピークですが、生育の遅れもあって上旬いっぱいに終えるようにしましょう。なお、房咲き種(FL)で一枝の開花を揃えるために頂蕾を摘むと書かれている本がありますが、あまり根拠はなさそうです。
■咲きがら摘み
5月中旬以降、晴天だと夏日(25℃以上)になるので、開花速度が早まり、満開の時期を過ぎると咲きがら摘みが忙しくなります。美観と株に負担がかからないよう、実を付けないように頻繁に摘むように心がけます。来客が多いお庭の場合は1日おきには摘むようにしたいものです。対象はすべてのカテゴリーで四季咲きのGCやシュラブ、つるバラも放任すると花を付けなくなります。
■施肥と水遣り
鉢植えに対しても肥料は一番花が終わるまで休みます。水遣りは開花とともに葉面積も増えてくるので蒸散が激しくなるので、よく観察して乾きすぎないよう気をつけます。庭植えの株には施肥、水遣りとも不要です。
■除草
気温が高くなってくると雑草も繁茂します。常に小さなうちに除草するようにしましょう。開花前には一度きれいにしておき、3週間に1度は除草します。
■新苗の植え付け
4月に引き続き、新苗植え付けの適期です。まだ、幼い苗なので鉢である程度の大きさまで育ててやるために冬まで鉢で育ててから庭に下ろすようにします。とくにつるバラは、秋に短く剪定された大苗を植えるより、新苗から育てると来春に沢山の花が見られます。
◎以上の作業は関東以西の作業となります。北の地方や降雪地帯にお住まいの方はテキスト2、112ページの平均気温表をご覧いただき、時期をずらして作業しましょう。