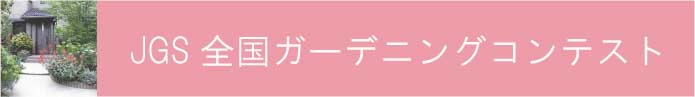◇ 1月のバラの手入れポイント ◇
新しい年を迎えると一段と気温が下がって本格的な冬の到来となり、月末から2月上旬が寒さのピークとなります。バラはすっかり葉を落とし、庭は冬枯れの様相が深まります。
休眠期の1/3は過ぎたので、この月も休眠期に済ませておくべき仕事をやり残しのないよう優先順位をつけて順次片付けましょう。
■冬の元肥
この時期に是非済ませておきたい作業です。
この時期は気温(地温)が低く、油かすや骨粉主体の有機質肥料は発酵、分解して
効果が出るまでに時間がかかりますので、発生するガスで根を傷める心配もありません。3月には効き始めてもらいたいので、1月下旬、遅くとも2月上旬までに施します。
配合原料には長期間ゆっくり効くよう、油かすや骨粉など有機質肥料が望ましいです。
バラの年間施肥量の大まかな目安としては1株当たりチッソ(N)30g、リン酸(P2O5)
90g,カリ(K2O)30gとされており、春の開花と夏の元肥までの必要量としてこの
2/3(チッソ20g、リン酸60g、カリ20g)を冬の元肥としてこの時期に与えます(1株
当たりチッ素として20gの目安は守ります)。
株数が多ければ油かす、骨粉、硫酸カリをそれぞれ買い求め、自分で配合すれば安くつきます。
株数が少なければ市販の配合肥料にリン酸を強化してチッソ:リン酸:カリの比率を1:3:1に近づけて与えます。
また1年に1回は有機物の補給をしたいので、この時期に腐葉土、牛糞、ピートモ
スのいずれか1株当たり5リットル程度を肥料と一緒に施します。なお同時に苦土石灰を適量(1平方メートル当たり150グラム程度)ばら撒いておけば酸度の調整に役立ちます。これらの施し方は深い溝を掘らなくともよく、有機物、元肥を株の間に置き、スコップで耕しながら反転させて鋤きこむ程度で十分です。この際
あらかじめ株元の雑草を始末しておけば作業がはかどります。
■大苗の定植・移植
新たに購入した大苗を望みの場所に定植します。植え付けは2月中に終われば問題ないです。気温が低いので、植えた後に芽が伸びてくる心配はありません。掘っ
た穴に有機物5~10リットル、配合肥料250g程度を入れ、土と混ぜた後、苗を植え、
水を10リットルやって完了です。もともとバラが植えてあった場所に植えるなら新しい土(バラが植わってなかったところの土)バケツ一杯ほどを根の周りへ包むように置いてやります。深植えにならないよう気をつけます。
一度植えた場所にミスマッチだった株は思い切って移植(植え替え)します。移植は手間がかかり、根を強く切り詰めるので、少し早めに行い根の回復に時間を見てやります。まずそのバラがその場所に適しているかを樹高や広がりを再確認します。 移植する株は強めの剪定を済ませた後、根を株の中心から半径30cmくらいに丸く切断して掘りあげ、植えなおします。その際根鉢を付ける必要はありません。
定植(植え付け)同様、植え穴に有機物、配合肥料を施します。
■鉢植えの土替え
鉢植えの土替え:植え替え同様根を切り詰めますので早めが望ましいのですが、寒地では鉢土が凍り、作業がやりにくいので暖かな日を選んで2月中旬には終えたいものです。鉢植えのバラはこの時期に新しい土に替えてやります。有機物を1/3ほど配合した土を用意します。元肥は原則として配合せず追肥として生育に応じて与えます。鉢から株を引き抜き、土をはたき落して根を鉢に収まる程度に切り詰め、植えなおします。この際、根を洗う必要はまったくありません。この土替えは毎年やるにこしたことはありませんが、隔年の場合は減った土に加えて有機物(牛糞な
ど)も補充してやりましょう。
■冬の剪定
冬の剪定は12月にしても3月にしても開花時期は殆ど変わらないので特に急ぐ必要はなく、いつでもよいのですが、2月中旬になると芽が膨らんで判別しやすくなるので2月中旬以降に行うとよいでしょう。
■つるバラの剪定と誘引
2月中旬以降になって気温が上がってくると芽が膨らんで誘引の作業中に欠けやす
くなりますので、今まだやっていないのであれば寒いうちに済ませます。
基本的には前年の誘引をすべてほどき、ゼロからやり直します。要点は欲張って残しすぎないこと、誘引するアーチやフェンスなどの構造物のスペースに必要な枝数を残し、古い幹から順に元から切り捨て誘引をし直します。誘引の順序としては古い幹、太い幹を先に誘引し、新しい幹、細い幹は曲げやすいので後に回す、下から上まで花で埋めるには細い枝を中心部と株元に配置します。枝幹は180度
〔水平〕から135度くらいに寝かせて誘引すると花つきがよくなります。枝間の距
離は20cm程度欲しいものです。
■予備剪定
2月に行う本剪定を楽にするため、あらかじめ古い幹や弱小枝を除去しておく作業です。別にやらねばならない作業ではないのですが、本剪定で長さだけをつめるようにしておけば能率が上がります。
■休眠期の病害虫防除
ボルンやマシン油乳剤などカイガラムシ対策が必要なら今月中旬までに済ませましょう。
■水遣り、除草など
庭植えの株にはまったく不要ですし、鉢植えも蒸散量が極端に減っているので10日以上雨のない場合以外遣る必要はありません。雑草は寒さにもめげず伸びてきますので、はびこらぬうちに除草します。
■接ぎ木、挿し木
これらの繁殖はこの休眠期が適期なので、凍らせない設備があれば是非行いたいものです。
芽が休眠している2月上旬までの寒い間が芽接ぎ、切り接ぎなどの接ぎ木の適期になります。ノイバラの台木或いは根が手に入ればぜひ接いでみましょう。接ぎ終わった苗は凍らないよう、また暖めすぎないように最低気温5゜C前後で管理します。スタンダードの接ぎ木は屋外に置かざるを得ないので春の彼岸ごろに行いますが、それまで芽が動かないよう1月に接ぎ穂を採って湿らせた紙に包み冷蔵庫に保存
しておきます。
◎以上の作業は関東以西の作業となります。北の地方や降雪地帯にお住まいの方はテキスト2、112ページの平均気温表をご覧いただき、時期をずらして作業しましょう。