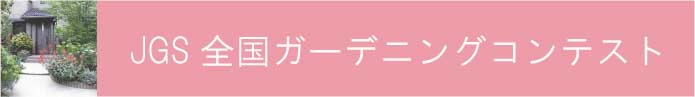◇ 2月のバラの手入れポイント ◇
上旬までは厳しい寒さが続きますが、日の長さは着実に伸びて日の出も早くなり、立春を過ぎると日差しに春の息吹が感じられるようになります。バラはこの日長の伸びを敏感に感じ取り、中旬以降には芽が急に膨らんできます。休眠期も最後の1ヶ月になりますので冬の作業を遣り残しのないよう急がねばなりません。優先順位を付けてこなします。
■冬の剪定
2月中旬から3月上旬が関東地方では剪定の適期とされていますが、これは芽がある程度膨らんでよい芽と悪い芽の見分けがつきやすくなっているからで、これまで述べてきたように休眠期ならいつでも構いませんし、12月にやっても、春のお彼岸にやっても開花時期はほとんど変わりません。 冬の剪定の要点はなんと言っても樹高を低く抑える、年に1回のチャンスですので思い切って切ります。ブッシュでは昨春の開花枝は1段目、その後発生したシュートはピンチして伸びた2段目で切るようにすると樹高を抑えることが出来ます。シュラブでは樹性に合わせ多少長めに残します。
やる手順としては
1. 主幹を更新するため、古い幹、枯れた幹を元から鋸で切り取ります。幹の数を制限するために昨年出たシュートの数だけ古い順に取り除きます。
2.弱小枝、内側に向かっている枝を取り除き、1箇所から複数出ている枝を1本にする(枝幹の密度を減らす)。
3. 上で長さを詰めます。昨年出たシュートは長めに残しますが、これまでの幹よりやや短めのところ、外芽の芽の上で切ります。箒状に伸びてしまったシュートは下の2本を生かして同様に3-4芽残して切る。昨年の開花枝は3-4芽残して外芽で切る。ピンチして伸びた側枝2本を3-4芽残して切る。太い枝は長めに、細い枝は短めにがコツです。
4. 最後に少し離れてみてバランスを調製する。
なお、この剪定は3月上旬までに終えれば十分です。
■冬の元肥
1月に元肥がやれなかった場合はできるだけ急いでなるべく上旬に済ませてください。遅くなるようなら分解を早めるためにコーランなどの発酵促進剤を使用するとよいでしょう。
■接木
接木の適期は2月中旬までが適期です。それ以降は芽が伸びてきて活着率が悪くなります。遅くなる場合は接ぎ穂にする枝を上旬に切り、穂木が萌芽しないよう早めに冷蔵庫へ(湿った紙に包んで)入れておきます。こうしておけばお彼岸のころスタンダードに接ぐこともできます。
■大苗の植え付け、植え替え、鉢の土替え
まだ間に合います。できるだけ早く、出来れば2月中に済むように進めます。土の配合は赤玉土(中)、有機物、庭土が1:1:1にしたら水はけ、水もちとも良く、プラ鉢ならごろ土は不要です。肥料は鉢土に混和せず、追肥の形でほぼ毎月与えます。
■つるバラの剪定、誘引
下旬になると誘引中に膨らんだ芽が欠けやすくなるので、まだ済ませてなかったら多少無理してもぜひ片付けましょう。遅くなると膨らみかけた芽が作業でぽろぽろと欠けますが、側芽が伸びてカバーしてくれます。やったやらないで大きな差がつきます。
■病害虫の防除
例年なら剪定後、休眠期の病害虫防除には、石灰硫黄合剤の濃厚液散布をすると黒点病の発生を大幅に遅らせるほか、カイガラムシの防除にも効果があるのですが、バラには適用がないということでお勧めできません。これに代わるものとして、マシン油乳剤やダコニール1000の濃厚液が薦められているようですが、効果はいかがなものでしょうか。こうなると病害虫ごとに適用薬剤を探すしかありません。たとえば、カイガラムシではアクテリック乳剤やマシン油乳剤を散布するなど、各自研究してみましょう。
■水遣り、除草など
下旬になると定期的に降雨が期待できますが、鉢植えの乾きすぎには気をつけます。雑草も気温の上昇とともに勢い良く伸びてきますので、大きくなる前に早めに除草します。
◎以上の作業は関東以西の作業となります。北の地方や降雪地帯にお住まいの方はテキスト2、112ページの平均気温表をご覧いただき、時期をずらして作業しましょう。